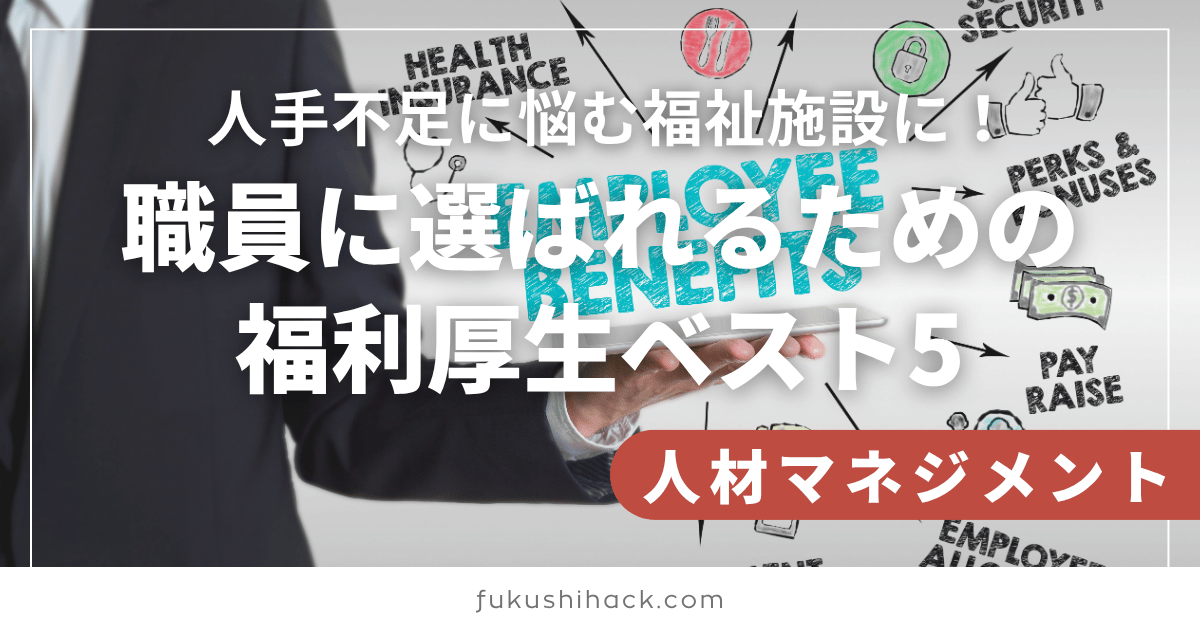もくじ
はじめに|“働きたい”と思われる職場とは?
福利厚生は“選ばれる職場”への第一歩
人材確保がますます難しくなるいま、福祉施設が“選ばれる職場”になるためには、待遇面だけでなく「働きやすさ」や「職員への配慮」が求められる時代になっています。特に若年層や子育て世代の職員は、給与以上に働きやすい環境や職場の風土を重視する傾向があります。
そうした背景から、注目を集めているのが福利厚生の充実です。今や「休憩室がある」「手当がある」といった制度だけでは十分とは言えません。職員の多様なライフスタイルに寄り添い、心身の健康を支え、スキルアップを応援するような福利厚生が、新たな採用・定着のカギとなっています。
この記事では、現場スタッフの満足度を高め、定着率の向上にもつながる「今こそ導入したい福利厚生」を5つ厳選してご紹介します。
相談支援専門員のフィールドレポート|“福利厚生の差”が現場に与えるもの
「“魅力的な職場”は、制度の裏にある」
「制度が人を集め、理念が人を残す」
そう感じたのは、さまざまな法人を訪問する機会が増えたここ最近のことです。
相談支援専門員として多くの法人に伺う中で、福利厚生の“格差”に驚くことが増えました。
ある法人では、残業が常態化し、シャドウワークのような見えない業務も多く、心身の余裕が削られている様子が見て取れます。一方で、別の法人では、フリードリンク付きの休憩スペース、資格取得支援、副業可など、思わず「羨ましい」と感じる制度が整っていました。
福祉業界は人材の流動が激しい分野です。
だからこそ、職場環境の差はそのまま「働く人の気持ちの差」になって表れます。
理想のCAFEを省スペースで!【自立型カウンターコーヒー JCC】印象的だったのは、40代以上の職員は「法人理念に共感して入社した」と語る一方、20代の職員は「福利厚生が決め手でした」と話していたこと。
理念や想いだけではカバーしきれない世代の価値観が、確実に変化してきているのを感じました。
たしかに、理念は組織の“魂”のような存在です。
でも、働く人にとって「制度」という“実体のあるやさしさ”があるかどうかは、安心して仕事を続けるための土台になります。
もちろん、制度だけで全てが解決するわけではありません。けれど、「働く人を大切に思っている」という意思が伝わる制度は、現場の空気を確実に変える力を持っています。
介護福祉士の国家試験に合格するならこのテキスト1冊だけで大丈夫!【受かるんです】相談支援専門員としてさまざまな現場を訪れる中で、制度が職場の空気や職員の表情にどれほど影響を与えるかを、肌で感じるようになりました。
「うちは社会福祉法人だから…」と諦めるのではなく、「福祉の現場だからこそ、職員を大事にする制度を」という視点が、今後ますます必要になってくるのではないでしょうか。
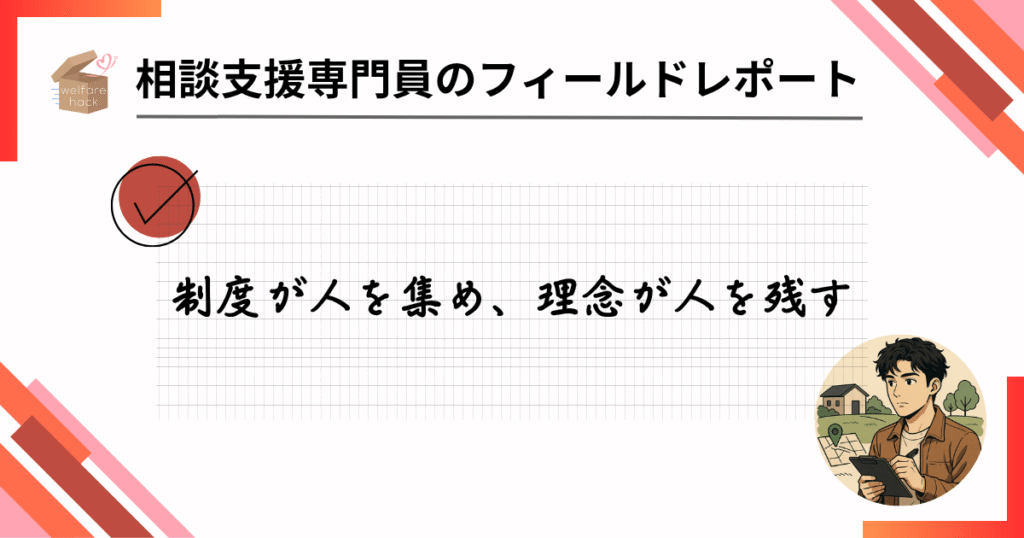
柔軟なシフト・勤務形態の導入
多様なライフスタイルに応える働き方改革
「家庭の都合で日中しか働けない」「週2回だけ勤務したい」など、職員のライフスタイルはさまざまです。特に子育て中や介護をしている職員にとって、柔軟なシフト制度は“働き続けられるかどうか”を左右する重要な要素となります。
短時間勤務制度、シフト希望提出の柔軟性、ダブルワークへの理解など、個々の事情に応じた働き方を可能にする仕組みを整えることが、離職防止と採用の両面に効果的です。
-
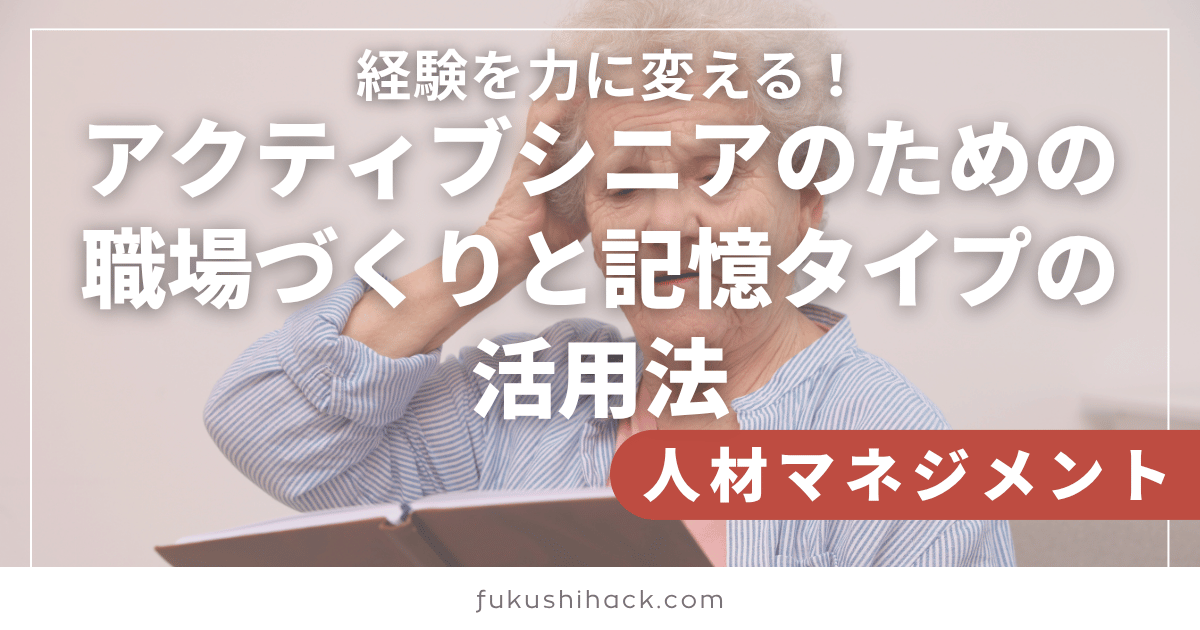
-
経験を力に変える!アクティブシニアのための職場づくりと記憶タイプの活用法
2025/8/2
アクティブシニアが活躍できる職場とは?記憶タイプの違いを理解して、経験を活かす働き方・職場づくりのヒントを紹介します。
また、週休3日制の導入や、フレックスタイム制などを取り入れる施設も増えており、「働き方を選べる」こと自体が大きな魅力になります。
制度を取り入れることは重要。でも、管理することもまた重要。
リラックスできる職場環境づくり(カフェスペースの設置など)

“心のゆとり”がチームの雰囲気を変える
福祉の仕事は心身の負担が大きく、リフレッシュできる環境があるかどうかで、仕事への意欲や継続意識が変わってきます。そこで注目されているのが、職場内に“ほっと一息つける”空間を設ける取り組みです。
カフェスペースやリラックスラウンジの設置、観葉植物や間接照明を取り入れた癒しの空間づくり、BGMやアロマの導入など、ちょっとした工夫で職場の雰囲気は大きく変わります。
このような“こころの余白”が生まれることで、職員同士の交流も深まり、チームの結束や職場への愛着にもつながります。
ドリンクサーバーやウォーターサーバーを導入している事業所増えましたね。特に就労B方は多い印象。
-
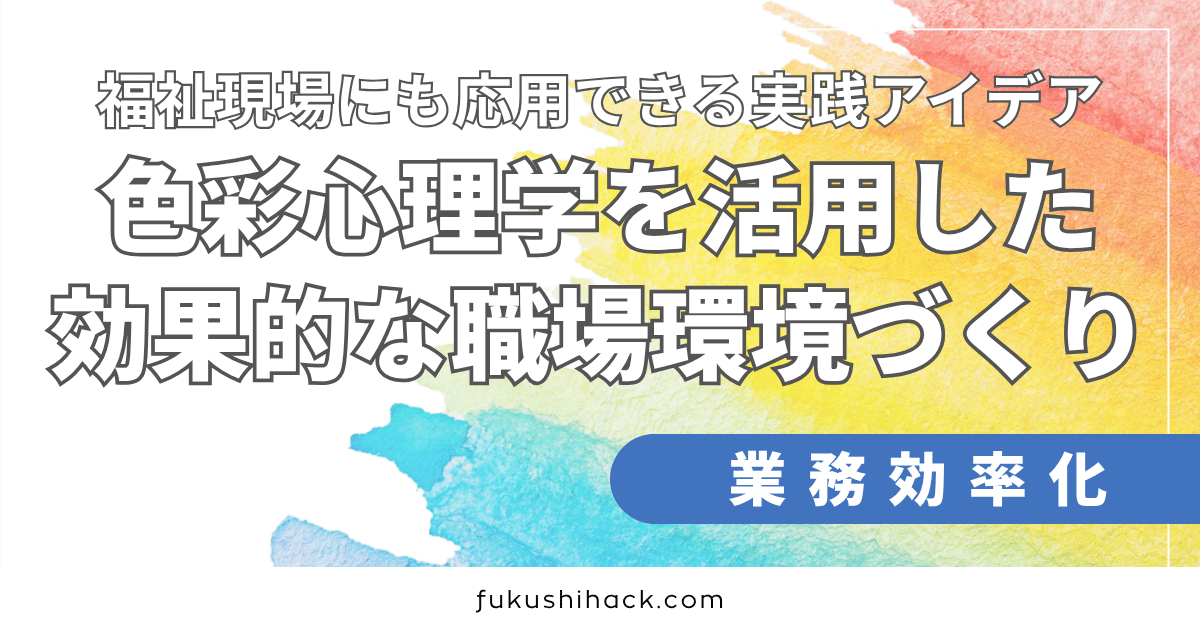
-
色彩心理学を活用した効果的な職場環境づくり|福祉現場にも応用できる実践アイデア
2025/8/19
色の力で職場が変わる!福祉現場やオフィスで使える色彩心理学の活用術。青・緑・黄色などの色で安心と集中をプラス。
スキルアップ・研修支援
資格取得・成長意欲をサポートする制度設計
介護福祉士や社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理師などの国家資格取得に向けた支援制度も重要です。施設が学びの場を提供することで、「この職場でキャリアアップできる」という安心感が職員の定着につながります。
介護福祉士の国家試験に合格するならこのテキスト1冊だけで大丈夫!【受かるんです】「この職場で働けば、自分が成長できる」そう感じてもらえる環境づくりは、職員の定着とモチベーション維持において非常に重要です。
資格取得のための受講費補助、外部研修の参加支援、eラーニングの導入、職場内研修の定期開催など、スキルアップを後押しする制度は、やる気のある人材を惹きつけます。
さらに、管理職向けのマネジメント研修や、若手育成のためのOJT制度の整備なども、次世代のリーダーを育てる基盤となります。
スキルアップしたいと考えるスタッフは大切にしたいものです。
-
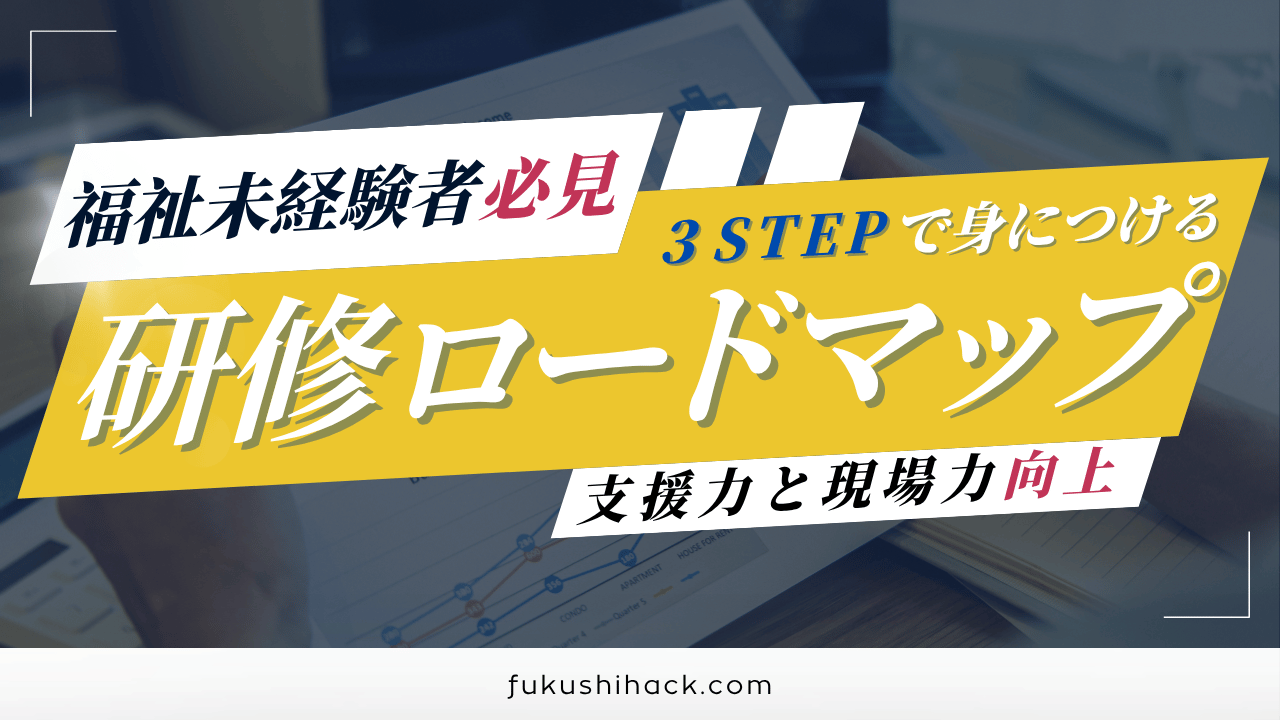
-
福祉未経験者のための研修ロードマップ|3ステップで支援力と現場力を身につける方法
2025/8/13
未経験から福祉業界で活躍するための3ステップ研修ロードマップを解説。支援の基本姿勢から対人援助スキル、セルフケアと職場環境改善まで網羅。転職希望者や新人研修設計に最適な内容で、現場力を高め長く働ける持続可能なキャリア形成を支援します。
記念日ギフト制度で“ありがとう”を伝える
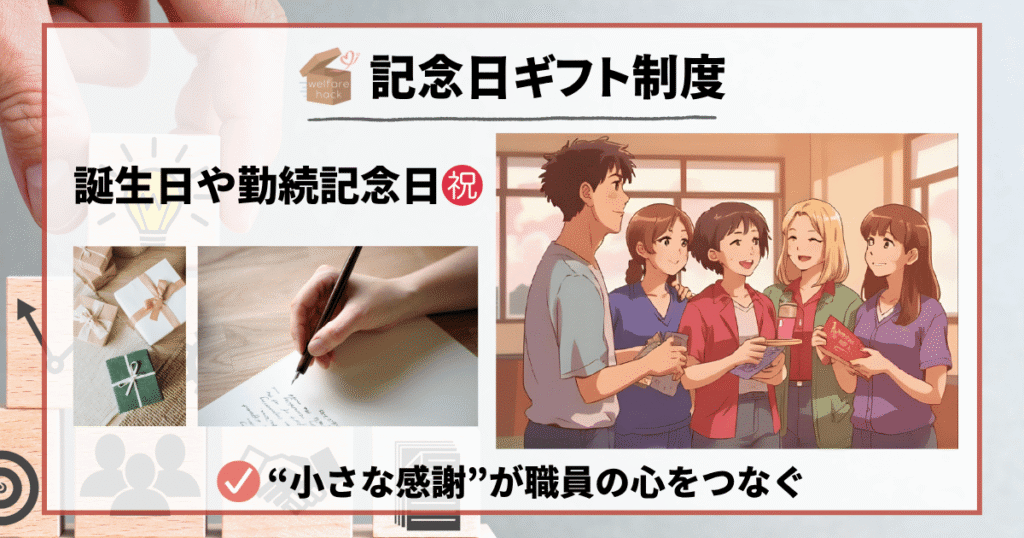
“小さな感謝”が職員の心をつなぐ
忙しい日々の中で、職員一人ひとりの存在をきちんと認める機会は意外と少ないものです。そんな中、誕生日や勤続記念日などにちょっとしたギフトを贈る制度は、「あなたを大切に思っている」という気持ちを目に見える形で伝えることができます。
コーヒーチケット、スイーツの詰め合わせ、リラクゼーショングッズなど高価なものでなくても構いません。大切なのは“気持ちを届ける”という姿勢。
このようなギフト制度は、職員のモチベーションや職場への愛着を高めるだけでなく、「ここで働きたい」と思ってもらえる雰囲気づくりにも効果的です。
直接「ありがとう」と伝えることも大切ですが、ギフトもまた気持ちが伝わって効果的。
副業・兼業OK制度
厚生労働省のガイドラインで制度化が後押し
働き方が多様化する中で、副業・兼業を認めることは、柔軟で自律的なキャリア支援になります。厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(令和4年7月改定)において、モデル就業規則に「勤務時間外に他の会社等の業務に従事できる」と明記し、副業・兼業を希望する労働者のスキル形成やキャリア選択を支援する方向性を示しています。(出典:「副業・兼業の促進に関するガイドライン」(厚生労働省)(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html)(2025年6月17日利用))
また、同ガイドラインでは労働時間の管理や健康状態の確認など、企業と労働者双方の配慮事項も明文化されており、「長時間労働にならないように」や「職務専念義務や秘密保持義務を考慮する」必要性も示されています。
多様なキャリア形成を支える柔軟な仕組み
福祉施設としても、この制度を導入しやすい環境を整えることで、職員が本業のスキルを高めながら新しい挑戦もできる働き方をサポートできます。就業規則の見直しや副業の内容の確認、労働時間と健康管理のルール整備をしっかり行うことが、制度導入のポイントとなります。
「スキルを活かして他の分野でも活躍したい」「家庭の事情で副収入が必要」など、さまざまな理由から副業を希望する職員は増えています。
副業を禁止するのではなく、就業時間外や業務に支障のない範囲で許可することで、職員の満足度や定着率を高めることができます。
制度化にあたっては、就業規則の整備やガイドラインの作成が重要です。また、副業を通じて得たスキルや経験が本業にも還元されるなど、プラスの効果も多く見られます。
中の人が勤める社会福祉法人でも副業解禁!ConoHa WINGを使用してブログ運営しています。
まとめ|福利厚生の充実は、“働きやすさ”の見える化
“今すぐできること”から始めてみよう
働き方改革が進む中で、“選ばれる福祉施設”には、給与だけでなく、職員一人ひとりの暮らしや気持ちに寄り添った配慮が求められています。
福利厚生は、その“やさしさ”を具体的に形にする手段のひとつ。特に紹介した5つの制度は、どれも大きな費用や仕組みを必要とせず、比較的導入しやすいものばかりです。
「今のままでいいのか?」と感じている経営者や管理者の方こそ、まずはできることから一つずつ始めてみてはいかがでしょうか。
-
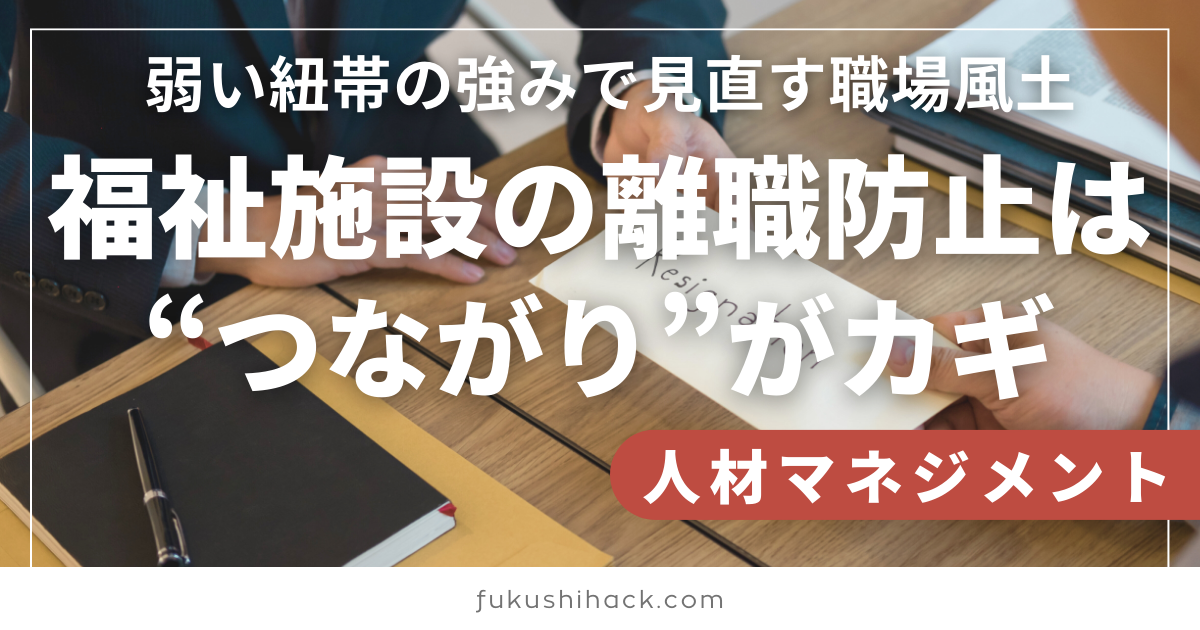
-
福祉施設の離職防止は“つながり”がカギ|弱い紐帯の強みで見直す職場風土
2025/7/16
辞めない職場は、“職場の外”につながりがある?管理者こそ知っておきたい「弱い紐帯の強み」の活かし方を解説。